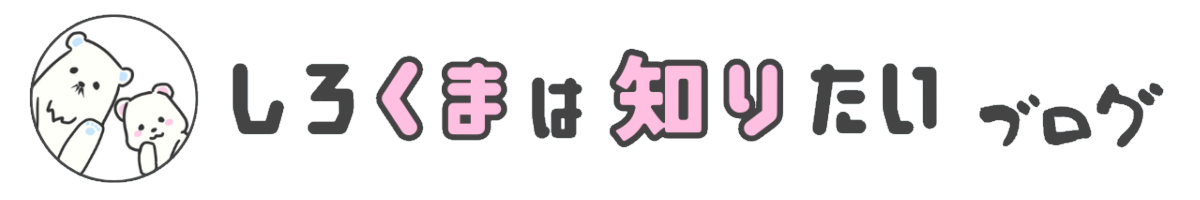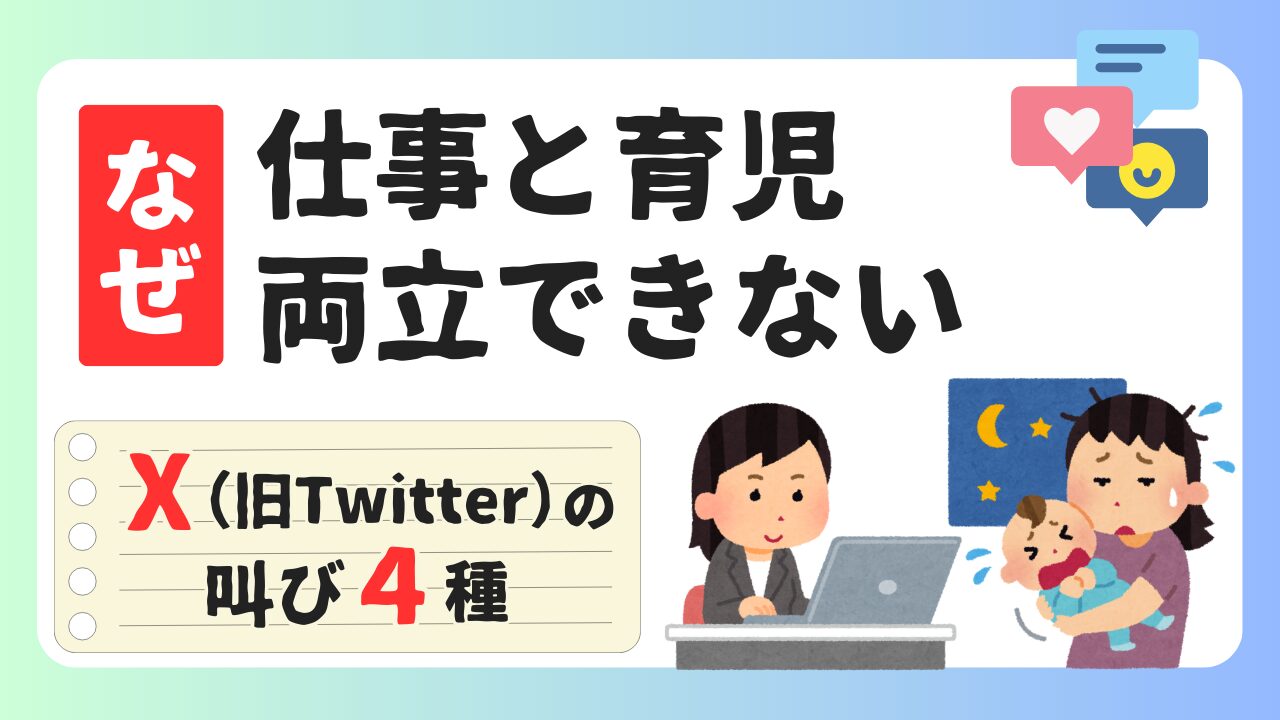2025年9月22日現在、X(旧Twitter)で、日本経済新聞の記事が話題になっています。
仕事と育児、なぜ両立できない? 長時間労働や賃金格差の是正進まずhttps://t.co/XRlAQmJCvo
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) September 20, 2025
タイトルだけを見ると「そんなの無理に決まってる!」と反応してしまう気持ち、よくわかります。
実際、SNSでは「できるわけない」という声が、その理由を添えて、たくさん投稿されています。
こうして多くの人が声を上げることはとても大切で、問題が社会の上層に届くきっかけにもなるはずです。
せっかく注目を集めたこの記事。
タイトルだけを見て、怒りや共感の反応をするのではなく、記事の本質がどこにあるのかも、きちんと見てみたいと思います。
発端|日本経済新聞のまとめ記事
事の発端となったのは、2025年9月20日に掲載された以下の記事。
仕事と育児、なぜ両立できない? 長時間労働や賃金格差の是正進まず
「少子化対策の盲点 負担の根源」まとめ読み
国が児童手当の拡充など少子化対策に取り組む一方、出生率低下が止まらない。
仕事と育児の「両立支援」が女性の就労を促すことに重きを置き、長時間労働の解消や男女の賃金格差の是正が不十分なのが一因だ。
政策に足りないものを女性、男性、子どもの目線から探った。
引用元:日本経済新聞
内容は、9月16日、17日、18日に掲載された会員限定記事「少子化対策の盲点 負担の根源(上)(中)(下)」を一気読みできるようにまとめたものです。
仕事と育児、なぜ両立できない?|3つの記事を考察
このまとめ記事につけたタイトル「仕事と育児、なぜ両立できない?」が、短い言葉で多くの人の心に突き刺さり、社会の矛盾を一瞬で浮き彫りにする力があるために、ここまで話題になったと思われます。
まとめ記事の内容については、会員限定の有料記事であるため、詳しく語ることはできません。
しかし、見える範囲の情報から、一つずつ考察していきたいと思います。
上|女性の目線
(上)スーパーウーマンにはなれない 緩い残業抑制、育児負担の偏りに悲鳴
2024年の日本人の出生数が70万人を割るなど少子化に歯止めがかからない。
残業や転勤が前提の働き方が変わらず、長時間労働と家事・育児をこなせない限り誰もが何かを諦めている。
両立支援や少子化対策に何が足りないのか。
「私は最前線に残るのを諦めただけ」
大手ゼネコンに勤める40代の女性は、第1子出産後に「うつ状態」と診断された。
花形の設計部で活躍していたが、子どもができて定時退社するようになり仕事が…(続きは有料記事)
引用元:日本経済新聞
女性の社会進出が求められている現代でも、家事・育児の多くを女性が担っているのが現実です。
仕事に全力を注ぎたくても、子どもが生まれた瞬間から(あるいは命がお腹に宿った瞬間から)、日々のタスクは一気に増え、長時間労働と家事・育児を両立するのは不可能な状況。
長時間労働と家事・育児をこなす「スーパーウーマン」でいられるのは一部の人だけで、多くの女性はどこかで何かを諦めざるを得ません。
記事に登場する女性が、花形部署にいながら育児との両立に疲弊し、「最前線に残るのを諦めた」と語っているのも、その象徴でしょう。
中|男性の目線
(中)令和男子「育休が無理なら転職」 両立の壁、性別問わず悩む
「やっぱりか」。
東京大学大学院に通う男性(24)は肩を落とした。
来春、就職する企業の先輩に育児休業について尋ねると、こんな答えが返ってきたからだ。
「奥さんが出産した日は1日休んだよ。翌日から出社したけど」
予想はしていた。
内定先は誰もが知る日本のトップメーカー。
仕事の魅力ややりがいにひかれて就職を決めたが、定時に帰れる職場ではない。
「みんな専業主婦の奥さんに子育ては任せきりなのだろう」と推測する…(続きは有料記事)
引用元:日本経済新聞
国の政策は「女性の就労促進」に重きを置いています。
児童手当の拡充、保育施設の増設など、一見進んでいるように見える施策もありますが、肝心の長時間労働の解消は手付かずです。
男性だって本当はもっと子育てに関わりたいのです。
ところが現実は、「定時で帰れない」「育児休業を取りづらい」という会社が、根強く残っています。
「奥さんが専業主婦だから任せているんだろう」と思われがちですが、実際には共働きでないと生活できない家庭が大半。
にもかかわらず、家事や育児の主な担い手は妻側に偏り、夫側は「関わりたいのに関われない」葛藤を抱えています。
仕事も家庭も大切にしたいのに、会社の仕組みや社会の前提がそれを許してくれない――。
そんな男性の声が、今の日本社会の「仕事と育児が両立できない」理由の一つを浮き彫りにしています。
下|保育士不足が生む「負のスパイラル」
(下)保育士数ぎりぎり「子供の安全守れない」 施設増えたが…足りぬ人手
「お子さんを迎えに来てください」。
東京都足立区に住む女性は1年ほど前、息子が通う保育園から連日呼び出しの電話を受けていた。
息子は発達に特性があり、たびたびかんしゃくを起こしてしまう。
「保育士が少なくてうちでは預かれない。他の子の安全を守れない」と言われ、もうダメだと悟った。
1歳児なら6人、3歳児は15人――。
国は保育士1人がみる子どもの数の上限を配置基準として示す。
基準より多く雇えば人件費の持…(続きは有料記事)
引用元:日本経済新聞
待機児童問題を解消するために保育園は増えましたが、肝心の保育士は足りていません。
保育士の仕事は、命を預かる仕事であり、長時間労働や心身への負担が大きい過酷な職業です。
その割に給与水準が低く、重労働のわりに待遇が見合わないため、成り手が少ない。
結果として、基準の上限ギリギリで、1人の保育士が多くの子どもをみなければならず、発達に特性がある子や手がかかる子がいると「もう預かれない」と言わざるを得ない状況に追い込まれています。
「保育士を増やせば解決するのでは?」と思いますが、低賃金や人手不足の現状ではそれも難しい。
施設を増やしても人材がいない――そんな矛盾が、子どもの安全や親の安心を奪っているのです。
補足|X民の反応
タイトルのインパクトもあって、今回の記事に対して、X(旧Twitter)でさまざまなコメントが飛び交いました。
子育て中の親の声、そして社会全体の仕組みに疑問を投げかける声など、多角的な反応が見られたところ、内容を整理すると大きく4つのカテゴリーに分けることができましたので、抜粋・整理してお伝えします。
ひとりひとりの叫びが集まることで、改めて「これは個人の問題ではなく社会の課題なのだ」と浮き彫りになります。
あなたはどう感じましたか?
まとめと感想|話題のタイトルから見えてくる本質
今回取り上げた「仕事と育児、なぜ両立できない?」という日本経済新聞の記事は、タイトルのインパクトだけでも大きな話題を呼び、Xでは多くの人が思わず反応して議論を交わしました。
実際の記事では、上・中・下の3つのパートに分かれ、女性の長時間労働と家事育児の負担、男性のジレンマ、そして保育士不足による子どもと家庭への影響という現実的な問題点を描き出しています。
X民のコメントには、「フルタイム共働きは物理的に無理」「労働時間を減らしてほしい」「母親ばかりに負担が偏るのはおかしい」「男性ももっと育児参加できる社会に」といった、日々の実感に基づく声が多数見られました。
元ネタである日経新聞の記事の本質は「制度や社会の仕組みが個人に過剰な負担を押し付けている」ということにあります。
タイトルだけで盛り上がるのも当然でしたが、内容に目を向ければ、私たちが働き方や育児支援をどう見直すべきかを考えるきっかけになる記事だと言えるでしょう。