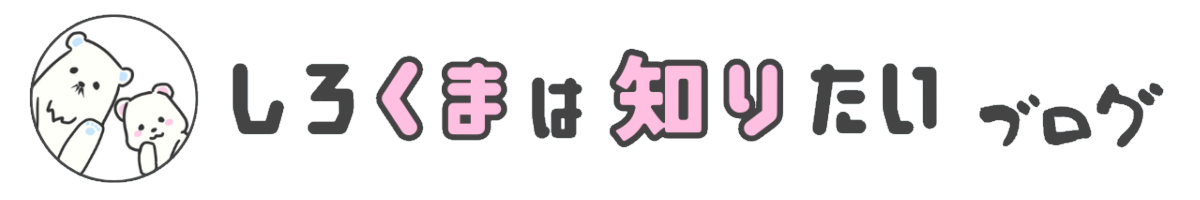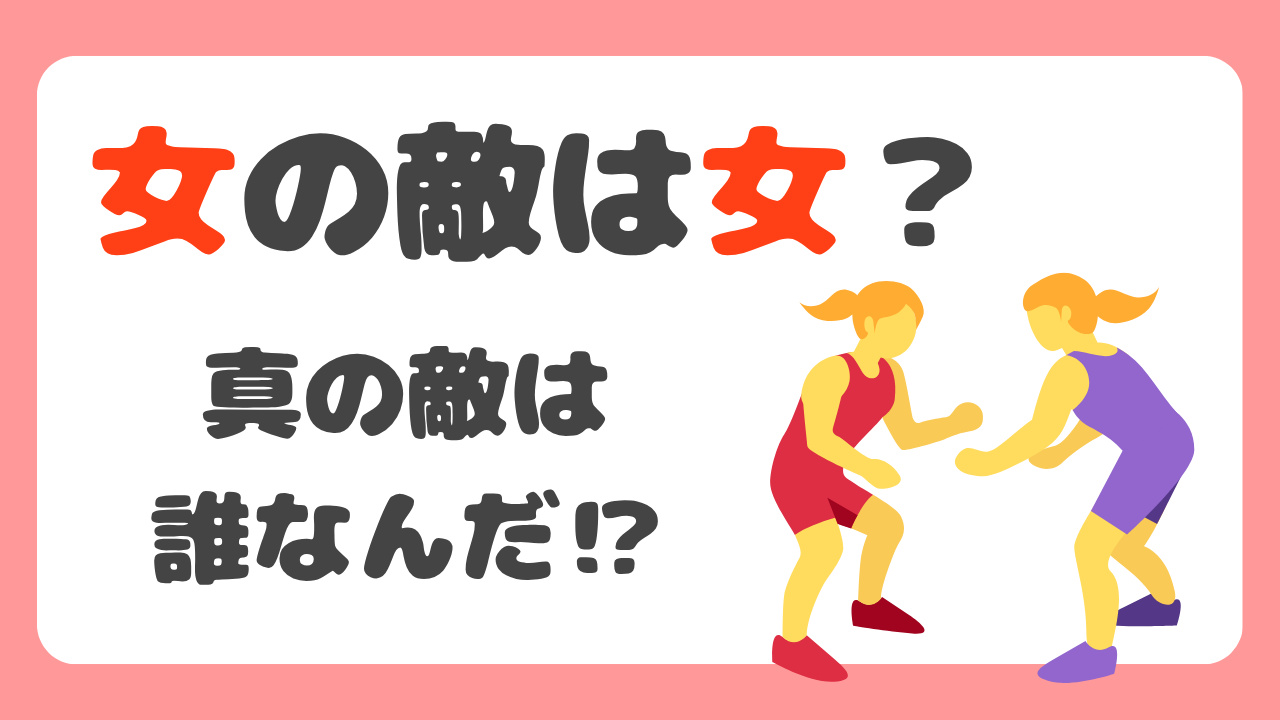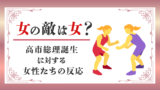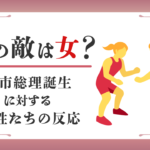高市早苗総理大臣に対して批判的なコメントをする女性政治家や有識者たちをきっかけに、
「女の敵は女」という言葉がトレンドワードになりました。
まあまあ、よく聞く言葉だけど、いつも少しモヤっとするんですよね。
心理学や社会構造の視点から調べた上で、考えてみました。
▼「女の敵は女」について考えたきっかけは、こちらの記事から▼
「女の敵は女」の身近な例
「女」とか「男」とか、勝手にカテゴライズしないでよ!
と、反発したくなってしまう言葉「女の敵は女」ですが、確かに、そう感じることがあります。
恋愛、仕事、育児、友人関係など、ちょっと「モヤッ」とする瞬間が、誰にでもあるのではないでしょうか。
まずは、「女の敵は女」だと思う身近な例を挙げてみました。
恋愛:好きな人の奪い合いでの嫉妬
たとえば、気になる人の近くにいる、他の女性の存在が気になってしまったり。
友達が自分より異性に好かれているようなとき、「ちょっと悔しい」という気持ちが芽生えてしまったり。
嫉妬や不安は、男女問わず持っている自然な感情ですが、「女性」という部分のみを切り取って、
「女の敵は女」と言われてしまうことがあります。
仕事:同僚や後輩への足の引っ張り合い
職場では、同僚や後輩の女性が自分より評価されているのを見て、ついライバル意識を持ってしまったり。
「あの子、最近頑張りすぎじゃない?」「ちょっと可愛いからって」なんて陰口の一つも言いたくなるもの笑
評価やポジションを巡る心理的な張り合いは、男性同士でもあることですが、
女性の場合は「女の敵は女」と表現されやすいです。
育児:ママ友グループでの比較・張り合い
赤ちゃんが、生後◯か月で歩き始めたとか、言葉を話したとか。
あるいは子どもの習い事や成績。
そしてママ自身の家事や育児の頑張りぶりなど。
そんなことで、ママ友との間に競争心が生まれることもあります。
「うちの子がまだ歩かないのは私がダメだから?」「あのママは完璧すぎる…」と感じた瞬間、
なんとなく逃げ出したくなったり。
些細な発言がマウントや嫉妬に感じてしまうのも、あるあるかもしれません。。
友人関係:自分より目立つ女性へのモヤモヤ
友人グループや趣味の集まりなどでも、「あの子、なんだか最近輝いてるな」と思った瞬間、
モヤモヤした気持ちが湧くことがありませんか?
「自分も頑張らなきゃ」と思う反面、比べてつい嫉妬してしまった経験もあるのではないでしょうか。
このように、日常のあちこちで、女性同士の小さな衝突やモヤモヤは生まれます。
「女の敵は女」と言われる場面は、誰にでも日常的に起こりうる現象です。

電子コミックの広告とかでよく見る
「自分より下に見ていたお姉さまの政略結婚の相手がハイスペ!キーっ!」
みたいなの、「女の敵は女」あるあるだよねぇ笑

漫画だと、「心の綺麗なお姉さま」の方に感情移入するから、
意地悪な妹が冷たくあしらわれてるのを見てスカッとするんじゃけどのう笑
心理学的に見る「女の敵は女」
「女の敵は女」と聞くと、女性同士が嫉妬や競争でギスギス・ドロドロしている光景を想像してしまいますが、
心理学的に見ると、これは女性だけに起こる現象ではないようです。
ただ、比較の矛先が、自分と立場や状況が近い女性に向きやすいというだけなのです。
① 同族嫌悪
「同族嫌悪」という心理があります。
自分と似た人ほど強く意識し、つい比較してしまう性質です。
女性の場合、社会から「美しさ」「母性」「社交性」といった基準で評価されやすいため、
女性同士の比較が激しくなりやすいのだそうです。
② 希少性理論
社会的・職業的な場面における「女の敵は女」については、男性優位の社会構造も無視できません。
長い間、女性は、「昇進や昇給のポストが少ない」「重要プロジェクトへの参加権がない」など、
限られた地位や権利をめぐって、競わざるを得ない状況でした。
この「希少性」の心理が、女性同士の小さな対立を増幅させます。
つまり、女性同士が争うのは「女性固有の問題」ではなく、男性中心の社会で生まれた現象だと言えます。
③ 社会的比較理論
現代ではSNSも影響しています。
キラキラした投稿を見て「私よりあの人の方がすごい」と感じることはありませんか?
心理学の「社会的比較理論」によると、人は自分の価値を測るために他者と比較する傾向があります。
この比較が過剰になると、嫉妬や敵意として表れることがあります。
大事なのは、これら「同じ属性同士での対立」は、男性同士でも起こるということです。
男性がライバルを意識したり、同期や同僚と張り合ったりするのも、同じ心理メカニズムです。
「女の敵は女」という表現は目立ちやすいものの、心理学的には、性別に特有な現象ではないのです。
なぜ「男の敵は男」とは言わないのか?
「女の敵は女」というフレーズは、わりとおなじみの表現になっていますが、
ではなぜ「男の敵は男」とは言われないのでしょうか。
① 男性同士の競争は、個人単位で語られる
もちろん、男性同士にも、職場の出世争いやスポーツ、恋愛の世界などで、競争や嫉妬はあります。
しかし、男性の場合は、個人の行動や性格として語られ、「男」という性別で括られることは少ないです。
男性の争いは、「男だから」という理由で一括りにされることはほとんどなく、
性別に関係なく、「あの人がライバル」「あの同僚に負けたくない」と、個人単位で語られることが多いのです。
結果、性別ではなく「ライバル」や「後輩」「同僚」として整理されるため、
言葉としての「男の敵は男」は定着しにくいようです。

そこだよ!
どうして男性は「個人」で語られるのに、女性は「女は〜」で語られるモフ?
② 「女」は文脈などで使われやすい
言葉としての「女」は、時にネガティブな文脈で使われやすい傾向があります。
「女は嫉妬深い」「女は怖い」「女は感情的」といった、長い歴史の中で作られた「ステレオタイプ」は、
昔から、物語やドラマ、ニュースの見出しなどでもよく登場してきました。
そのため、「女同士の争い」や「女の妬み」といったネガティブな話題が出ると、
「女の敵は女」というフレーズが使われやすくなります。

確かに、男性には「男らしさ」という概念はあるものの、
ネガティブな文脈で日常的に使われることは少ないのう
こうしたネガティブワードに限らず、古くから日本では、
男性目線で「女」という言葉が便利に使われる場面が多くあります。
たとえば、前時代の「女の幸せは結婚」「女は家庭向き」「女らしくあれ」といった表現は、
女性の生き方を限定し、行動や価値観を縛る役割を果たしてきました。
一方で、男性側からしても、「女はこうあるべきでしょ」と、都合よく家事や育児などの
面倒ごとを女性に押し付ける効果もあったり。

男女関係なく競争や対立は起きるけれど、
女性に限っては、それを言語化するときに「女性は〜」って枠に入れてしまうんだのう
まとめ|「女」の本当の敵は「比べさせる社会」
結局、「女の敵は女」なんて言葉が生まれるのは、
女性同士が比べ合うように仕向けている、社会のせいかもしれません。

あっ…なんでも「社会のせいだ!」って言っちゃうのは、
厨二っぽくて少しむず痒いモフ…
「女はこうあるべき」という「枠」に押し込められて生きていると、他の女性のことが気になってしまう。
本当の敵は、女性同士ではなく、
人を比べさせたり、枠に押し込めたりする社会の空気そのものなのではないでしょうか。
本来、「女性は女性の仲間」だと思うんです。
同じようなことに興味を持ったり笑ったり、同じような悩みを持って奮闘してきた「同志」です。
比べあって競争するより、支え合う方がきっとずっと心地いい。
そんなあたたかさが広がれば、「女の敵」なんて言葉はいらなくなるはず、と思います!
▼「女の敵は女」について考えたきっかけは、こちらの記事から▼