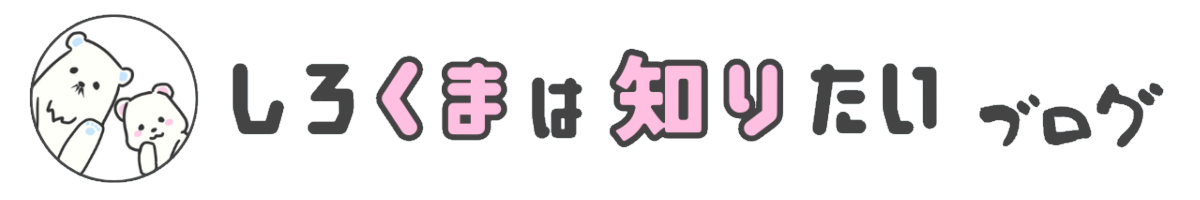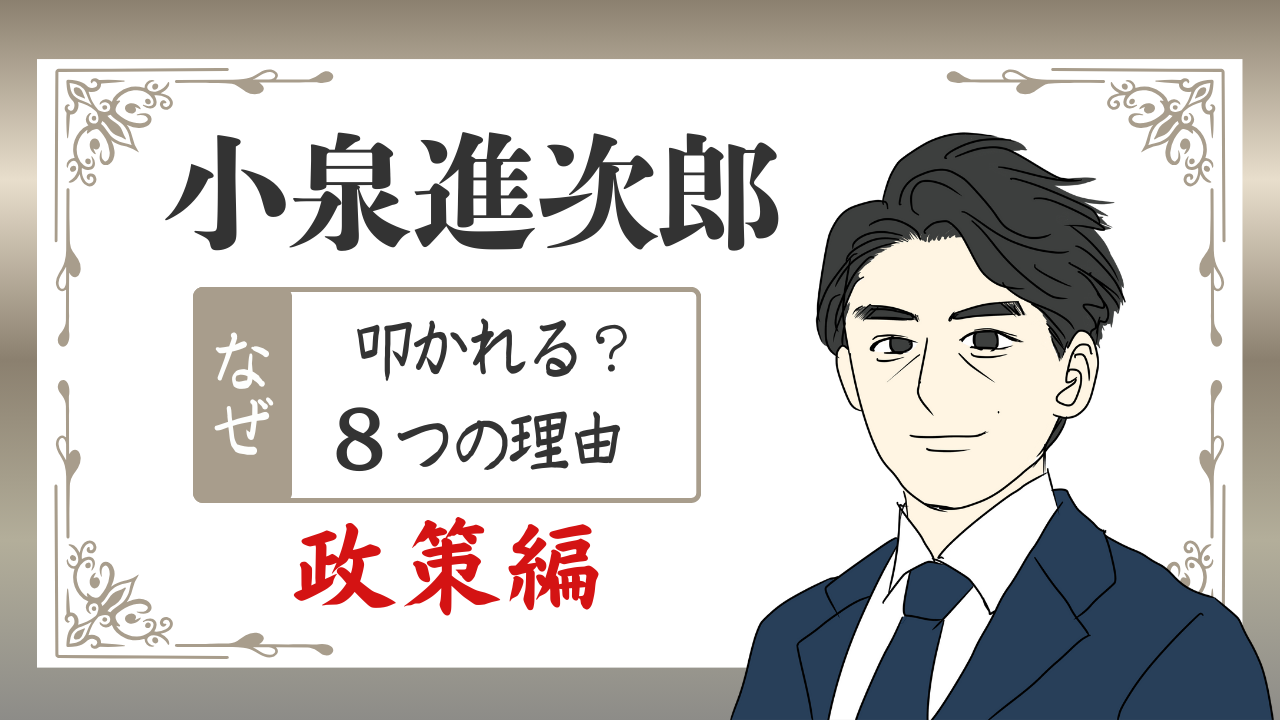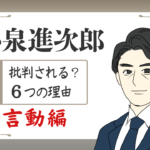10月の自民党総裁選に出馬し、最有力候補とされている小泉進次郎氏。
ところが2025年9月26日、陣営による「ステマ疑惑」が報じられ、「総裁選辞退」がトレンド入りするほど大きな反響を呼びました。

小泉進次郎さんって、とってもカッコいいお顔なのに、どうしていつも批判されてるモフ?
X(旧Twitter)で、アンチコメントをよく見るモフ〜
小泉氏をめぐっては、今回に限らず、発言や行動が何かと批判の的になりやすいのが特徴です。
なぜ彼はこんなに批判されやすいのか――。
この記事では、小泉進次郎氏が「なぜ叩かれやすいのか」という理由を、これまで小泉氏が行ってきた政策等の面から、わかりやすく解説していきます。
そして最後に見えてくるのは――「叩かれるのも人気の裏返し」という、進次郎氏ならではの宿命かもしれません。

小泉進次郎さんが政治家として何をしてきたのか。
政治に詳しくない筆者が、頑張って調べてまとめたぞい!
小泉進次郎が叩かれやすい理由8選(政策編)
小泉進次郎氏は、なぜこんなに叩かれやすいのか――。
ここでは、すでに「プロフィールや経歴」の記事でご紹介した小泉進次郎氏の情報を前提に、
政治家・小泉進次郎が行ったとされる政策等のうち、ネットやX(旧Twitter)で批判の対象になっているものをピックアップします。
1. 農協改革(2015年〜)
小泉進次郎氏は、自民党農林部会長時代、「儲かる農業」をテーマに、農協改革や農業の競争力向上など、党内での方針づくりに取り組んだことが知られています。
日本の農協は、農家のために資材を安く提供する組織として設立されたはずですが、いつしか、資材販売や農産物の買い取り、銀行業務まで手がけ、農家よりも自らの利益を優先する構造になっていました。
小泉氏はこれを問題視し、全農の資材購買部門の縮小や農産物販売方式の見直しを盛り込んだ改革案をまとめ、最終的には「農業競争力強化プログラム」として政府方針に反映され、農協側の自主的改革を促す形となりました。
この改革は、農協という戦後最大級の圧力団体に挑むもので、実行状況や成果が注目される一方、農業現場や一部メディアからは「実務に即していない議論ばかりで、農家の現実を知らない」と批判されることがありました。
改革や効率化の議論は賛否が分かれるテーマでもあり、小泉氏自身の目立ちやすさや言葉の端々、提案の仕方が注目されやすかったことも、批判を受けやすい理由と言えるでしょう。
2. 「人生100年時代構想」(2018年10月〜)
小泉氏は、2018年10月に自民党の厚生労働部会長に就任して以来、「人生100年時代に向けた新たな社会保障の実現」に力を入れています。
少子高齢化が進む中で、従来の「学ぶ・働く・引退する」という人生モデルでは社会が立ち行かなくなるという問題意識から、学び直しや転職、柔軟な働き方を可能にする仕組みを提案しました。
新卒一括採用や定年制度といった「レール」に縛られない、多様な選択肢を持てる社会を目指すというのが、小泉氏が打ち出したビジョンです。
しかし、この「人生100年時代」という理念は、そのまま称賛されるだけではありません。
小泉氏の政策は「未来志向で革新的」と映る一方で、「抽象的で誤解されやすい」という二面性を持っています。
その結果、支持と批判が表裏一体となり、常に議論を呼ぶ存在となっているのです。
3. レジ袋の有料化(2020年7月〜)
小泉進次郎氏が環境大臣を務めていた2020年7月、日本全国でレジ袋の有料化が義務化されました。
これは「プラスチックごみ削減」や「炭素税の導入に向けた意識づけ」を目的とした施策で、実際に、環境省の調査によれば、レジ袋の使用量は大幅に減少し、マイバッグ利用率も7割を超える水準に達しました。
国民の行動変容を促したという点では一定の成果を上げたといえます。
しかし一方で、レジ袋自体は家庭ごみ全体のわずか数%しか占めていなかったことから、「環境効果は限定的」という批判もあります。
こうした反発に対し、小泉氏はこう説明しました。
申し訳ない。是非ご理解頂きたいのは、レジ袋を全部なくしたところでプラスチックごみ問題は解決しない。それが目的ではなく、有料化をきっかけに一人一人が問題意識を持ってもらいたい。
この発言は、当初、レジ袋の有料化による「プラスチックごみの削減」を目的としていたのに、後付けで「効果そのものは狙っていなかった」と説明しているように映り、責任逃れのように感じられました。
結果として、レジ袋有料化は、環境政策としての効果には疑問が残る一方で、人々の暮らしや意識に大きな影響を与えた政策として、今もなお、議論の的であり続けています。
4. 国立公園内での太陽光発電の規制緩和(2020年10月)
小泉進次郎氏は、環境大臣であった2020年に、国立公園内での再生可能エネルギー発電所設置に向けた規制緩和を表明しました。
この方針は、日本政府が2020年10月に宣言した「カーボンニュートラル」
=「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする」という政府目標に沿ったものです。
具体的には、全国34の国立公園の多くが発電所の新設を制限している中、地熱や太陽光、風力などの再生可能エネルギーを活用しやすい地域であることから、保護と利活用の両立を目指し、発電所設置の規制を緩和する方針が示されました。
小泉氏が環境大臣を退任した後の2022年3月30日に、環境省が「国立・国定公園内における太陽光発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」を施行して実現しています。
報道で注目されたのは、主に太陽光パネル(メガソーラー)です。
自然環境の保護と再生可能エネルギーの導入を両立させるための前向きな取り組みと評価される一方で、
国立公園は自然環境の保護が最優先されるべき場所であり、発電所設置による環境破壊や希少種の生息地への影響が懸念されたのです。
熊本県と周辺7市町村は、熊本・阿蘇山の世界文化遺産登録を目指していますが、その南側に福岡ドーム17個分のメガソーラーが出現。
牧野の表土剥ぎ取りや木の伐採で自然景観が大きく損なわれ、住民からも憤りの声が上がっています。
2025年9月、北海道の釧路湿原国立公園周辺では、大規模太陽光発電所(メガソーラー)による国の特別天然記念物のタンチョウを含む生態系への悪影響が懸念され、釧路市から「希少な野生生物の生息調査が不足している」との指摘を受けた日本エコロジーは、工事を一時中断しました。
2025年9月、政府はメガソーラーの規制強化などを検討する関係省庁連絡会議開き、全国各地で地域との共生に課題があるとして、省庁が連携して解決策を探ることが確認されました。
このように、小泉氏の国立公園内での再生可能エネルギー発電所設置促進政策は、環境保護とエネルギー政策の両立を目指すものでしたが、実際には自然環境への影響や地域住民との調整など、多くの課題を抱えていたことが明らかとなりました。
5. 「解雇規制の見直し」公約(2024年9月)
2024年9月の自民党総裁選で、小泉進次郎氏は「大企業の解雇ルールを見直して、人材の流動性を高める」と公約に掲げ、来年の国会提出を目指すと宣言しました。
具体的には、企業は解雇に踏み切る前に希望退職者の募集や配置転換の努力をすることが義務付けられていますが、これを大企業に限って撤廃し、代わりにリスキリングや再就職支援を課すという内容です。
この発言に対して批判も多く、「解雇規制の緩和=自由解雇ではないか」と不安視する声があります。
そもそも整理解雇の要件は裁判例で示されているもので、法律上は明確に規定されておらず、大企業に限定して制度を変えること自体の実現性も疑問視されています。
一方で賛成の意見もあります。
小泉氏の発言は、法制度や労働慣行の現実と合わせて考えると、批判と賛成の双方が理解できる玉虫色の内容です。
今後、具体的な法案の提示や運用方法次第で、評価は大きく変わるかもしれません。
6. 備蓄米の放出(2025年5月〜)
小泉進次郎氏が2025年5月に農水大臣に就任すると、同年2月から行われていた備蓄米の放出は、よりスピード感を持って推し進められました。
備蓄米放出には、2024年から始まった米価高騰の中で、消費者の家計負担を軽くし、物価を抑える狙いがありました。
政府が備蓄米を、通常の米の流通ルートではなく、スーパーなどの小売業者に直接販売する形を取ったことで、消費者・世間の注目を集め、「政府が動いた」という安心感も生まれました。
しかし、30万トンの米を急いで販売した結果、この放出方法には問題も指摘されています。
結局、備蓄米放出は「消費者向けの価格抑制」という目的と「備蓄米を早く売る」という行為が混同し、政策としての整合性が問われる結果に。
消費者支援や農家支援という国の役割と、販売方法の現実的な影響とのバランスが難しい課題であることを浮き彫りにしました。
7. 農協解体の噂(2025年8月頃〜)
SNSで「小泉進次郎が農協を解体して150兆円を外資に差し出す」といった話が流れていますが、これは事実ではありません。
2025年9月5日の衆院農水委員会で小泉農水相自身が、「農協を外資に差し出すことは全くない」ときっぱり否定しています。
問題になっているのは、農協改革の方向性であり、小泉氏は「農家に必要とされるサービスを提供する組織があれば、それが農協でも、別のプレイヤーでも構わない」と説明。
つまり、農家が選べる仕組みを作りたいという考えです。
ネットやSNSでは、小泉氏の発言の文脈やニュアンスが切り取られたり、誰かの憶測が混ざったりすることがあり、単純化された陰謀論が広がりやすく、「農協を潰す」と誤解されがちですが、小泉氏自身は農協を応援し続ける姿勢を明確にしています。
8. 議員立法ゼロ(2025年3月)
インターネット上でよく見かける小泉進次郎氏への批判のひとつに、「議員立法ゼロ」というものがあります。
つまり「15年も国会議員をしていながら、自ら法案を一本も提出していない」という指摘です。
きっかけは2025年3月にX(旧Twitter)に投稿されたツイートで、これが「政策をつくれない」「口だけ」といったイメージにつながり、SNSで瞬く間に拡散されていきました。
ところが、これは正確ではありません。
日本ファクトチェックセンターの調べでは、小泉氏はこれまでに 少なくとも5件の議員立法 を提出しており(2025年4月現在)、「ゼロ」という主張は誤りだとされています。
そもそも、成立する法律の大半は内閣提出法であり、与党の国会議員は議員立法を出すこと自体が少ないのが実情です。
与党議員は、内閣提出法案に与党審査という形で関わることで、自身の考えを反映させることができるので、議員立法案は政府野党が提出することが多いのです。
成立した法案数が少ないという点は事実ですが、それだけを切り取って「仕事をしていない」と断じるのは、公平さに欠けると言えるでしょう。
もちろん、小泉氏自身が注目されやすいキャラクターであるため、数字や実績がシンプルに批判材料にされやすい面もあります。
しかし、「議員立法ゼロ」という言葉だけで判断するのではなく、政府内での役割や実際の活動内容も合わせて見ることが大切だと思います。
まとめ|小泉進次郎は賛否を呼ぶ政治家
小泉進次郎氏が、その政策等の面から批判されやすい理由は、以下のとおりでした。
- 農協改革
◯「農業競争力強化プログラム」として政府方針に反映
×「実務に即していない議論ばかりで、農家の現実を知らない」と批判 - 「人生100年時代構想」
◯柔軟な働き方を可能にする仕組みを提案
×年金や医療制度が不安定になるのではないかと警戒 - レジ袋の有料化
◯プラスチックごみに対する国民の行動変容を促した
×プラスチックごみの削減に対する効果は限定的 - 国立公園内での太陽光発電の規制緩和
◯環境保護とエネルギー政策の両立を目指す
×実際には自然環境への影響など、多くの課題を抱えていた - 「解雇規制の見直し」
◯働く人への新しいキャリア機会を提供する前向きな改革
×「解雇規制の緩和=自由解雇ではないか」と不安視 - 備蓄米の放出
◯政府がスピード感を持って実行した
×本来の目的である「市場の安定」「農家支援」が十分に果たされなかった - 農協解体(噂)
農協を解体するとは言っていない
必要なサービスを提供する組織を農家が選べる仕組みを作りたい - 議員立法ゼロ(事実ではない)
実際は5件の議員立法を提出している
「仕事をしていない」と断じるのは公平さに欠ける
政策を振り返ると、成果や狙いがあった一方で、現実とのギャップや誤解、時にはデマによって批判が大きくなった面も見えてきます。
小泉さんが叩かれやすいのは、その発信力や注目度の高さゆえでしょう。
賛否の声が混ざり合う中で、私たち有権者も事実を丁寧に見極める姿勢が大事だと思います。